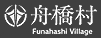廙嫶懞怑堳尋廋
戞5尷栚
廙嫶懞偺尰忬暘愅嘋
恖岥摦懺嘊憤妵
抧堟峔憿嘆怴偨側榑揰,峀堟揑側懞偺億僕僔儑儞
奐嵜擔帪丗暯惉25擭10寧22擔乮壩乯18丗00乣20丗00
応強丗廙嫶懞栶応丂2奒夛媍幒
暯惉25擭搙廙嫶懞怑堳尋廋5擔栚偼,廙嫶懞偺尰忬暘愅偺怴偨側帇揰偲偟偰抧堟峔憿偺娤揰偐傜億僕僔儑儞傗棫抧摿惈傪夝柧偟,栚巜偡傋偒峀堟揑側曽岦傪扵傞偲偲傕偵恖岥憹壛偺懚棫婎斦傪嵞峫,恖岥栤戣僾儘僕僃僋僩偺僷乕僗儁僋僥傿僽傊偺摙媍偑側偝傟偨丅

抧堟峔憿暘愅
乣廙嫶懞偺峀堟揑側億僕僔儑儞乣
暘愅扴摉丒幒棖岺嬈戝妛巗懞尋媶幒
夝愢丗晉嶳戝妛抧堟楢実悇恑婡峔丂嫵庼丂嬥壀徣屷
廙嫶懞尰忬暘愅偺怴偨側帇揰偲偟偰,條乆側僨乕僞傪梡偄偰廙嫶懞偲椬導巗挰懞偺摿惈偺峔憿壔傪恾偭偨幒棖岺嬈戝妛巗懞尋媶幒偑暘愅扴摉偟偨帒椏僨乕僞傪夝愢丅
峀堟揑側尒抧偐傜摿挜傪扵傞庤朄偲偟偰巗挰懞暿僨乕僞偺懡曄検暘愅偵傛傞抧堟峔憿攃埇曽朄偑偁傞偲徯夘丅懡曄検暘愅偼抧堟摿惈側偳暋崌揑嶌梡傪峫椂偟,庡惉暘暘愅偲僋儔僗僞乕暘愅偵婎偯偒抧堟峔憿偺峀堟揑側尒抧偐傜偺摿挜傪専弌偡傞丅抧堟峔憿暘愅偺巜昗偲偟偰梡偄偨晉嶳丒愇愳丒婒晫丒怴妰偺巗挰懞偺奺庬僨乕僞帒椏傪墈棗偟,廙嫶懞偺尰忬偲嬤椬丒峀堟巗挰懞偲偺堘偄傗帡捠偭偨晹暘傪攃埇丒嵞妋擣偟偨丅
恖岥斾棪偱偼15嵨枹枮偍傛傃65嵨埲忋恖岥斾棪偲帺慠憹壛棪偺摿堎惈,扨撈悽懷斾棪傗65嵨埲忋偺恊懓偺偄傞妀壠懓悽懷斾棪,拫栭恖岥斾棪側偳偵摿挜偑偰偰傞偙偲傪媞娤揑偵妋擣丅夘岇榁恖暉巸巤愝悢傗恾彂娰枾搙乮柺愊乯偺懠巗挰懞傛傝撍弌偟偰偄傞摿挜丄堛椕婡娭悢傗梒曐巤愝悢偺忬嫷,忢廧1恖摉偨傝偺彜揦擭娫斕攧妟傗峴惌偺嵿惌椡巜悢側偳偺斾妑側偳偺帒椏僨乕僞偐傜廙嫶懞偺尰忬傕嵞妋擣偟偨丅偝傜偵帒椏僨乕僞偵婎偯偒摑寁揑偵帡捠偭偨巗挰懞傪椶宆壔偟偨僋儔僗僞乕暘愅寢壥偐傜廙嫶懞偺撈帺惈偲嬤帡巗挰懞傪扵傝,廙嫶懞偺峀堟揑側億僕僔儑儞傗摿挜傪専摙丒摙媍偟偨丅傑偨,崙惃挷嵏偺捠嬑捠妛棳摦挷嵏僨乕僞偵傛傞搒巗峔憿暘愅寢壥偐傜晉嶳導偍傛傃椬愙偺愇愳丒婒晫丒怴妰偺奺搒巗娫偺1師棳摦丒2師棳摦丒3師棳摦偺恖偺棳傟傪攃埇偟,搒巗偺栶妱傗抧堟峔憿偺尰忬傪柧妋偟,搒巗偺偮側偑傝偵偮偄偰傕尰忬傪妋擣偟偨丅
抧堟峔憿暘愅僨乕僞傪庴偗偰偺慡懱偺摙媍偱偼,廙嫶懞偲帡捠偭偨帺帯懱偵偮偄偰傗媞娤僨乕僞偵傛傞摿惈丄嬤椬偺巗挰偲偺堘偄傗壽戣側偳偑偁偘傜傟,廙嫶懞偺峀堟揑側億僕僔儑儞傗摿挜偵偮偄偰偺擣幆傪嫟桳偟偨丅嬥壀嫵庼偐傜乽廙嫶懞偩偗偱側偔嬤椬巗挰偺僨乕僞傕岻偔巊偭偰恑傔偰梸偟偄乿偲傾僪僶僀僗丅媑揷巵偼乽偙傟傜偺帒椏傪巤嶔偺僶僢僋傾僢僾僨乕僞偲偟偰妶梡偟偰梸偟偄乿偲榖偟偨丅

僨傿僗僇僢僔儑儞
廙嫶懞偺尰忬暘愅
恑峴丗晉嶳戝妛抧堟楢実悇恑婡峔丂嫵庼丂嬥壀徣屷
戞2夞栚偐傜崱夞傑偱偺4夞偵搉偭偨廙嫶懞偺尰忬暘愅傪暅廗偟,擭戙暿偺曄壔傗恖岥曄壔偑懞偵婲偙偡曄壔,恖岥曄壔傊偺懳墳偵偮偄偰摍恖岥摦懺偲崱屻偺曄壔偵偮偄偰偺嵞妋擣傪偍偙側偄,偙傟傑偱傗偭偰偒偨廙嫶懞偺尰忬暘愅傪摑崌壔偟偰奺恖偑乽帺暘偺尵梩偱榖偣傞傛偆偵偟偰梸偟偄乿偲嬥壀嫵庼傛傝巜帵丅廙嫶懞恖岥憹偺梫場偱偁偭偨戭抧奐敪偱慖戰億僀儞僩偱偁偭偨搚抧壙奿偺埨偝偵娭偟偰摉帪偲尰嵼偺忬嫷偵偮偄偰攃埇偡傞偨傔偵,廃曈抧嬫偲偺嵟嬤20擭娫偺抧壙岞帵壙奿偺斾妑僨乕僞偑椦巵傛傝採弌偝傟抧壙偺曄慗偲尰嫷,尰嵼偺嬤椬偺暘忳戭抧幚攧壙奿傗晄摦嶻嬈幰偺暦偒庢傝挷嵏偱偺忬嫷側偳徻嵶傪夝愢偟,尰忬偱偺壙奿柺偱偼懠抧堟偲斾妑偟偰妱埨姶偩偗偱廙嫶偼慖戰偝傟側偄偲榖偟偨丅
妱埨姶埲奜偱偺廙嫶偺枺椡偼壗偐傪傒傫側偱扵偟偰偄偔偙偲,棙曋傗嫵堢娐嫬丒杊斊懱惂摍偵偮偄偰摙媍丅懞偺愝旛傗僒乕價僗柺偱嵎暿壔傪恾傞昁梫惈,庒偄悽戙偱偺岥僐儈偱偺枺椡揱払側偳偑榖偝傟偨丅恖岥摦懺曄壔偲崱屻偺曄壔偱梊憐偝傟傞壽戣傗偦偺懳墳傊偺僗僀僢僠偲側傞巕堢偰悽戙懳墳,弌惗棪岦忋,崅楊壔懳嶔,嵿惌栤戣傊偺巤嶔偼壗側偺偐帺暘偨偪偱忣曬傪扵偟偰,廙嫶懞偺尰忬偵偮偄偰帺暘偺尵梩偱師夞傑偱偵傑偲傔傞傛偆壽戣偑偩偝傟偨丅傑偨師夞偐傜師偺僗僥僢僾偵堏峴偡傞偵偁偨傝,亀偳偺傛偆側懞傪栚巜偡偺偐亁亀彨棃恖岥偺愝掕傪偳偙偵偡傞偐亁偑偁傢偣偰壽戣偲偟偰偩偝傟偨丅
憤妵
尋廋偺5擔栚傪廔偊偰,椦巵偐傜乽懞偺恖岥栤戣偵偮偄偰條乆側梫場傪媍榑偟偨偑擄偟偄偙偲偩偗偳偦傟傜傪娭楢晅偗偟偰傑偲傔偰偔偩偝偄乿偲儊僢僙乕僕丅媑揷巵偐傜偼乽偙傟偐傜偼嫞偄崌偆帪戙栚愭偩偗偱側偔彨棃傕幚姶偱偒傞偙偲傪峫偊偰偄偭偰梸偟偄丅梌偊傜傟傞娐嫬偵偼尷奅偑偁傞丅峴惌偼偳偆傗偭偰偄偗偽偄偄偺偐峫偊,廬棃偺堦曽曽岦僒乕價僗偩偗偱側偔峫偊捈偡帪偵偒偰偄傞丅乿偲憤妵傪偍偙側偭偨丅